【実録】散歩中のひっぱり、歩かない、ビビり癖…プロドッグトレーナーがそんな悩みをまるごと解決!

人間社会にまったく慣れていない、社会化トレーニングもままならない保護犬を迎え入れた時、
「散歩中に引っ張って逃げようとする…」
「そもそも散歩しているのに歩かない」
「音や声、他の犬や飼い主さんにビビりまくっている…」
というトラブルが生じ、どこからどう対処すべきなのか悩んでいませんか?
保護犬を迎え入れると、しつけや社会化トレーニング、新しい環境に慣れさせようとしてまず散歩から始めようとするので、上記のようなトラブルがあるととても困ってしまうことでしょう。
今回は、歩かない・引っ張る・ビビり癖という保護犬あるあるのお散歩の問題点を解決する、とっておきの方法を伝授!
このコラムをチェックしておけば、保護犬ならではのお散歩時の悩みがまるごと解消できますよ。
ぜひ、最後までご覧になってくださいね。
動画でも詳しく解説しています!↓
目次
散歩で保護犬が歩かなくなるのはどうして?ふたつの原因があった!
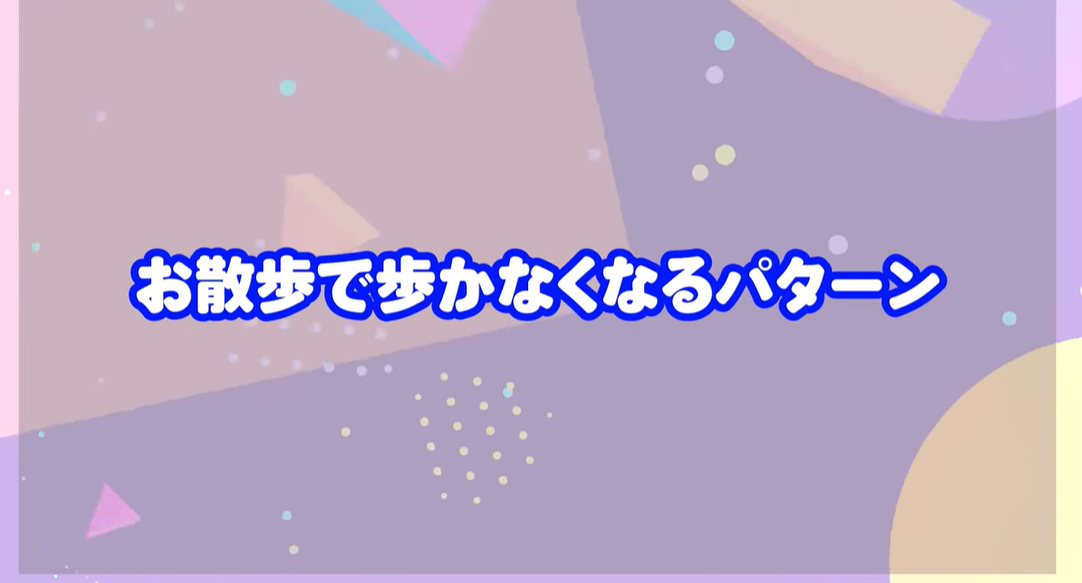
人間社会に慣れていないことが原因、というイメージが強い保護犬のお散歩中のトラブルですが、飼い主さんが意外に気づけていなかった原因がふたつあります。
気になるそのふたつの原因が、
- 恐怖や緊張によるもの
- ワンちゃんのワガママによるもの
が深く関係しています。
では、上記2つの原因がお散歩のトラブルにどう関係しているのか、気になる理由を見ていきましょう。
怖い、緊張という原因
お散歩中に愛犬が歩かない、逃げようと引っ張る、ビビッてしまうというトラブルが生じてしまうのは、「怖い・緊張」という原因が大きく関係しています。
社会化トレーニングを済ませていたり、普段からたくさんの人や他の犬、モノ・音に慣れている犬の場合は、それが自身にとって当たり前の環境のため、上記のような問題ナシにスムーズにお散歩できます。
ですが保護犬の場合はこれまでとまったく違う環境に置かれ、お散歩や社会化トレーニングがままならないことが影響し、初めての経験に好奇心よりも恐怖や緊張が強く出てしまっているのです。
ワンちゃんのワガママによるもの
お散歩をしているつもりが、他の所に行こうとしてリードを引っ張ったり、歩かないといった問題行動が頻繁に出てしまうのは、「ワンちゃんのワガママ」が大きく影響しているのかもしれません。
普段から愛犬優先の日常生活を送っていたり、頻繁におもちゃやおやつをあげるといった甘やかしてきな接し方をしていると、愛犬との主従関係が崩れ、ワンちゃんの方が飼い主さんよりも立場が上のような関係性になってしまいます。
すると、そのワガママはお散歩時にも反映されてワンちゃんの行きたい方に行く、逆に飼い主さんが散歩されている状態に…。
ワガママになってしまうとお散歩という感覚がなくて歩かなくなったり吠え癖・飛び出し・飛びつきといろいろな問題行動につながるおそれがあるため、注意が必要です。
歩かない・引っ張る・ビビり癖のお散歩トラブル…正しい解決策【シャイな犬編】
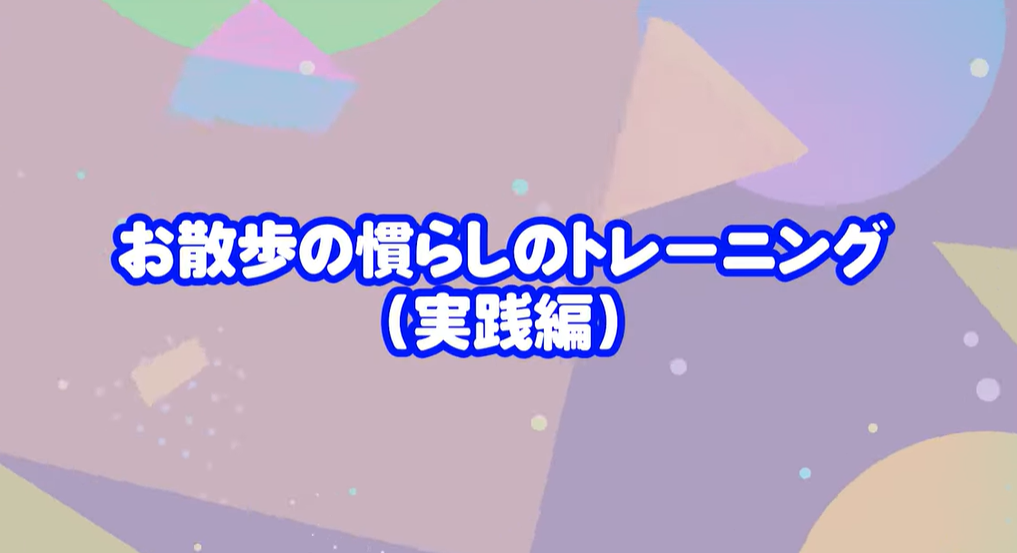
お散歩中に歩かない・引っ張る・ビビり癖のトラブルが出ている際は、愛犬の性格やその原因に応じた正しいしつけ・解決策を取ることが重要です。
ここではシャイで怖がり、緊張しがちな愛犬編、歩かない・引っ張る・ビビり癖の正しい対処法をまとめてみました。
「大丈夫だよ」の声がけを繰り返し伝える
シャイな性格でお散歩のたびにおっかなびっくりしている愛犬には、カラダを撫でたりトントンとしながら「大丈夫、怖くないよ」の声がけを繰り返ししましょう。
飼い主さんが常にそばにいて、大丈夫だよと安心させるような声がけ、トントンとやさしいスキンシップを繰り返すうちに、愛犬はお散歩は怖くない、楽しいひとときと少しずつ認識を変えていきます。
そして愛犬がなかなか歩かない、座り込んでしまったとしても、シャイで慎重、怖がりな性格を考慮して待ってあげることも意識的に行いましょう。
この積み重ねがシャイで怖がりなワンちゃんへ安心を伝えるきっかけになり、徐々に良い変化に気付けるようになりますよ。
慣らしのトレーニングを習慣にしよう
シャイで臆病、慎重なワンちゃんはもちろん、興奮癖がある愛犬の対処にも効果的なのが、「散歩に対しての慣らしのトレーニング」です。
お散歩はこれから、ワンちゃんに摂って日常茶飯事になるため、生活の一部・社会化トレーニングのひとつなのだと学びを認識させることが重要。
ここでは慣らしのトレーニングが実際にどんなものなのか、気になる内容ややり方、目的をまとめてみましたのでぜひ参考にしてくださいね。
焦らず落ち着いて対処する

ワンちゃんが歩かない、座り込む、お散歩コースから外れるといったトラブルがあると、ケガや事故、他の飼い主さんに迷惑がかかるのではないかと焦り、パニックになってしまいますよね…。
ただ、飼い主さんがパニックになって焦ると、普段から親同様に飼い主さんを見ている愛犬はその変化に呼応して一緒に興奮、パニックになるおそれがあります。
一緒にパニックになっていては収拾がつかなくなるので、まずは落ち着いて冷静になる意識を強くしてみましょう。
犬は飼い主さんに呼応する性質があるため、飼い主さんが落ち着いていればワンちゃんも倣って落ち着く、そんな状態がルーティンになるはずですよ。
リード・ハーネスのサイズを確認
シャイなワンちゃんはもちろん、お散歩中に興奮しがちなワンちゃんにも効果的な習志野トレーニングが、「リード・ハーネスのサイズ確認」。
この理由は、ワンちゃんにとってサイズに違和感のあるリード・ハーネスは、居心地が悪いことで戒めから逃れようと興奮したり他のところに逃げようとする、いろいろなトラブルにつながってしまいます。
リード・ハーネスはサイズに合ったものを選ぶことで愛犬のお散歩がスムーズになり、締め付けられているといった違和感を感じずにワンちゃんも快適なお散歩時間を楽しめるでしょう。
原因に対してのアプローチをすること
歩かない、引っ張る、ビビり、興奮などのお散歩中の愛犬トラブルは、必ずと言っていいほど原因があります。
- うるさい音がして怖い
- リード、ハーネスの圧を感じる
- 疲れている、帰りたい
- 他の飼い主さん、犬が怖い
- 他に行きたいお散歩コースがある
などなど、これらの原因を見極めてお散歩時の環境やコース、時間やタイミングなどを見直し・調整しましょう。
お散歩中の愛犬のストレスをできるだけ取り除き、心地よいお散歩をすることが理想のため、問題行動の原因と対処をひとつひとつクリアしてくださいね。
噛むタイプのおもちゃ、おやつを活用
音にびっくりしたり歩かなくなる、ビビり癖などのシャイなワンちゃんには、「噛むタイプのおもちゃ、おやつ」を活用してみることがおすすめです。
意外に知られていないのですが、おもちゃやおやつを犬が噛む行為は、興奮や緊張を鎮めるリラクゼーション的な効果が期待でき、リラックスすることで飼い主さんの指示・しつけを聞いたりコミュニケーションが取りやすくなります。
どんな犬でも噛む、という行動は本来の習性でリラックスの基本となるため、お散歩時には噛むおやつ・おもちゃを常備しておくとよいでしょう。
歩かない・引っ張る・ビビり癖のお散歩トラブル…正しいしつけ【わがままな犬編】

続いては、ワガママなワンちゃんにありがちな歩かない・引っ張る・ビビり癖のお散歩トラブルに対する、正しいしつけをチェックしてみましょう。
お散歩の主導権をしっかりと握ること
ワガママになってしまっている愛犬のお散歩時の自由気ままな行動は、「主従関係」をしっかりとさせ、お散歩中の主導権を握ることが絶対的なポイントになります。
飼い主さんがワンちゃんを可愛がり、何でも言うことを聞いて溺愛してしまうがゆえにワンちゃんのお散歩中のワガママが発動している状態。
この状態をリセットすべく、リードやハーネスをつけて愛犬を良い意味でコントロールしながら、飼い主さんに行きたい方に進んでワンちゃんをリードしてみましょう。
飼い主さん主導のお散歩ができたら褒める
飼い主さん主導をお散歩で愛犬を自然にコントロールし、愛犬も飼い主さんのペースに合わせて歩くようになったら、
- 思いっきり褒める
- 「いい子だね、えらいね」となでなでしてあげる
- 愛犬の好きなおもちゃ、おやつのご褒美をあげる
という対策を採ってみましょう。
この流れを何度も繰り返すうちに、安定した主従関係がキープでき、ワンちゃんも「飼い主さんにペースを合わせたらいいことがあった」とプラスの学び、成功体験を得てお散歩中のワガママや問題行動の解決につながりますよ。
リードは「短く持つ」ことが基本
愛犬が興奮していたり、歩かない、急に止まって座り込む、そんな問題行動があるのはリードの持ち方も関係していること、ご存じでしたか?
そして、愛犬の興奮を抑えようとした時のリードは、「長く持って愛犬をリラックスさせる」という対処が正しいと思っている方が大多数…。
実はこの対処は大きな間違いで、「愛犬が興奮している時ほどリードは短く」が基本なんです。
リードを短く持つことで興奮している愛犬をコントロールしやすくなったり、飼い主さんとの距離が近くなって指示やしつけ、コミュニケーションが取りやすくなります。
リードを長く持つのは逆に、
- 愛犬が自由になっていきたい方向に行ってしまう
- 距離が離れすぎて指示やコミュニケーションが取りにくくなる
という悪影響で余計にお散歩中の問題行動が悪化してしまうため、短く持ったリードでコントロールを心がけましょう。
おわりに

今回の東京DOGSコラムでは、保護犬やワガママになってしまったワンちゃん、シャイな性格のワンちゃんのお散歩中によくある、歩かない・引っ張る・ビビり癖といった解決策をお伝えしてきました。
お散歩は愛犬とコミュニケーションを楽しみ、信頼関係を深める重要なポイントになるため、本コラムを繰り返しチェックしながら問題行動の正しいしつけを始めてみてくださいね。
動画でも詳しく解説しています!↓
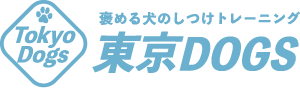
 ごあいさつ
ごあいさつ ブランド・理念
ブランド・理念 スタッフ紹介
スタッフ紹介 会社概要
会社概要 求人情報
求人情報 犬の預かりしつけ教室
犬の預かりしつけ教室 犬の保育園・幼稚園
犬の保育園・幼稚園 犬のペットホテル・ドッグホテル
犬のペットホテル・ドッグホテル パピーパーティー
パピーパーティー 出張しつけ教室
出張しつけ教室 犬のしつけ教室(来店型)
犬のしつけ教室(来店型) 各種オプションメニュー
各種オプションメニュー 法人様向け
法人様向け 初回カウンセリングの流れ
初回カウンセリングの流れ サービスのご案内
サービスのご案内 東京DOGS -越谷本店-
東京DOGS -越谷本店- 東京DOGS-春日部本店-
東京DOGS-春日部本店- 東京DOGS-足立-
東京DOGS-足立- 東京DOGS-浦和-
東京DOGS-浦和-